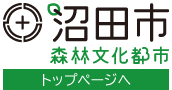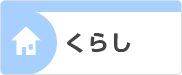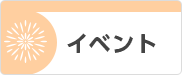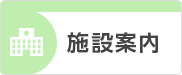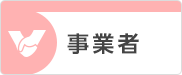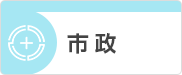沼田市南郷の曲屋(旧鈴木家住宅)
南郷の曲屋について

鈴木家の先祖は、当地に熊野神社を建設するために神官として来村、定着し、代々名主を務め、政治家などを輩出してきました。当家は検地などで訪れる役人の逗留施設でもあり、主屋の上段の間には、付け書院、帳台構えを設け、武家の好んだ正式な書院造りがなされています。
主屋は、東北地方の民家でよく見られる曲屋(まがりや)形式で、突起部分は「うまや」となり、神経質な馬の健康状態を常に把握できるようにしていました。県内では珍しいかやぶき屋根の曲屋形式の民家です。
建物の正確な建造年代は不明ですが、敷地内の稲荷社の側壁に「天明5年10月大吉日」とあることや建築手法などから検討した結果、天明5(1785)年)に竣工したと推測されます。
平成16年3月8日には、市の重要文化財として指定されました。
母屋

この建物は、岩手県などの雪国でよく見られる、かやぶき屋根の民家で、母屋に対してL型に曲がっているところから、曲屋と呼ばれるようになりました。L型に曲がっている部分は、「うまや」として数頭の馬の飼育に使われてきました。
かやぶき屋根とは、ススキなどの草で屋根をふいた住宅のことです。さらに、養蚕のため、2階に床を張るなど、増築・改修を重ね現在の形になりました。
オクノデイ

上段の間である「オクノデイ」は、ほかの部屋より段が高くなっており、主賓が着座し、ほかの来客は主賓に近い人から、オクノデイに近い「ナカノデイ」に着座しました。
正面にオドコ(雄床)、メドコ(雌床)を設け、向かって左手には付け書院を、これと対応した右側には敷居を一段高めた「帳台構え」を設け、武家の邸宅に好んで採用された正式な書院造りを構成しています。このような正式な書院造りは県内にも類がなく、特筆すべき貴重なものです。
土蔵

ウエノ蔵、シタノ蔵、新蔵の3棟とシタノ蔵に接続してみそ蔵の4つの蔵があります。
土蔵(どぞう)とは、外壁を土やしっくい(石灰に麻の繊維などを加えた物)などで塗り固めて建てられた、日本の伝統的な保管庫、倉庫のことです。主に火災や盗難防止のために建てられ、後に、裕福さの象徴として建てられることもありました。
現在では、当時使用した民具・農具などの展示を行っています。
水車小屋

水車は、主に脱穀(収穫した稲などを茎からはずすこと)・製粉(小麦を砕いて粉にする)・製糸(糸を作ること)など、生活のために使われていました。
ご案内
- 開館時間:午前10時~午後4時(通年)
- 休館日:木曜日(木曜日が国民の祝日にあたるときはその前日)、年末年始(12月29日~1月3日)
- 入館料:大人110円、小人50円(中学生)
小学生以下及び障がい者は無料 - 所在地:沼田市利根町日影南郷158番地1
電話:0278-54-8611
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経済部 観光交流課 利根観光係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表)ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください