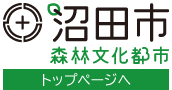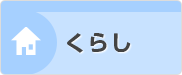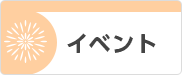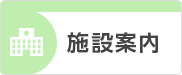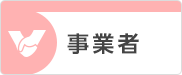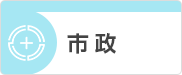福祉医療制度(重度心身障がい者・高齢重度障がい者)の見直しについて
医療費が増え続ける状況の中、福祉医療制度を将来にわたって安定的に維持するため、制度の見直しが行われました。
みなさまのご理解をお願いいたします。
令和5年8月改正 所得の基準(所得制限)導入について
令和5年8月から、本人または住民票上同一世帯の配偶者や扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)の対象所得が所得制限基準額を上回る方については、福祉医療制度の助成対象外となります。
対象所得:給与所得、事業所得、不動産所得、雑(公的年金等)所得、譲渡所得等
障害年金や遺族年金などの非課税所得は対象外
|
税法上の 扶養親族等 の数 |
受給資格者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
||
|---|---|---|---|---|
|
所得制限基準額(以下) |
給与収入額の目安 |
所得制限基準額(未満) |
給与収入額の目安 |
|
|
0人 |
3,661,000円 |
約5,252,000円 |
6,287,000円 |
約8,319,000円 |
|
1人 |
4,041,000円 |
約5,728,000円 |
6,536,000円 |
約8,586,000円 |
|
2人 |
4,421,000円 |
約6,204,000円 |
6,749,000円 |
約8,799,000円 |
|
3人 |
4,801,000円 |
約6,668,000円 |
6,962,000円 |
約9,012,000円 |
※給与収入は助成対象となる上限の目安額です。給与以外の所得、所得控除により増減します。
所得制限基準額は、扶養親族等一人につき一定額加算されます。
所得制限基準額は、特別障害者手当に準拠しているため、制度改正により変更となる場合があります。
判定方法
受給資格者本人または住民票上同一世帯の配偶者・扶養義務者(直系血族、兄弟姉妹)のいずれかの対象所得が所得制限基準額を上回るとき、助成対象外となります。
受給資格者本人の対象所得 ー 一定の所得控除 > 受給資格者本人の所得制限基準額 + 一定の扶養親族加算
または
配偶者・扶養義務者の対象所得 ー 一定の所得控除 ≧ 配偶者・扶養義務者の所得制限基準額 + 一定の扶養親族加算
一定の所得控除
所得控除のうち、下表の控除については、対象所得から差し引くことができます。
|
控除の種類 |
受給資格者本人 |
配偶者・扶養義務者 |
|---|---|---|
| 雑損控除 |
相当額 |
相当額 |
| 医療費控除 |
相当額 |
相当額 |
| 社会保険料控除 |
相当額 |
一律8万円 |
| 小規模企業共済等掛金控除 |
相当額 |
相当額 |
| 配偶者特別控除 |
相当額(最高33万円) |
相当額(最高33万円) |
| 障害者控除(本人) |
ー |
27万円 |
| 障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族) |
一人につき27万円 |
一人につき27万円 |
| 特別障害者控除(本人) |
ー |
40万円 |
| 特別障害者控除(控除対象配偶者・扶養親族) |
一人につき40万円 |
一人につき40万円 |
| 寡婦控除 |
27万円 |
27万円 |
| ひとり親控除 |
35万円 |
35万円 |
| 勤労学生控除 |
27万円 |
27万円 |
一定の扶養親族加算
税法上の控除対象扶養親族のうち、下表の扶養親族については、所得制限基準額に加算することができます。
|
扶養親族等の種類 |
受給資格者本人 |
配偶者・扶養親族者 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 老人扶養親族(70歳以上) |
一人につき 10万円 |
一人につき 6万円 |
配偶者・扶養義務者については、扶養親族が老人のみの場合は、一人を除いた人数 |
|
特定扶養親族(19歳以上23歳未満)または、一定の扶養親族(16歳以上19歳未満) |
一人につき 25万円 |
ー |
|
| 同一生計配偶者(70歳以上) |
10万円 |
ー |
平成31年4月改正 入院時食事療養費の助成について
平成31年4月から、入院時食事療養費の助成を受けるためには、県内・県外問わず、医療機関の窓口で「減額認定証」の提示またはマイナンバーカードによる電子資格確認により、一定の所得区分であることを証明する必要があります。
減額認定証とは
医療機関の窓口で提示することにより、入院時に支払う食事代が減額されるものです。主に住民税非課税世帯の方が対象となります。医療費の自己負担限度額を示す「限度額適用認定証」と兼ねている場合は、区分がオ、低所得者1、低所得者2のいずれかが記載されています。
減額認定証には有効期限があり、自動更新はされません。その都度、申請が必要ですので有効期限にご注意ください。(後期高齢者医療の方は自動更新されます。)
なお、マイナンバーカードによる電子資格確認により、住民税非課税世帯であることを確認できる方は、減額認定証の提示なしで食事代が減額されます。※電子資格確認は、令和3年3月から医療機関で順次利用が可能となります。設備が整っていない医療機関では引き続き減額認定証の提示が必要になりますので、ご注意ください。
申請と問い合わせは、保険証に記載されている保険者へしてください。
市役所で申請できます。マイナンバーカード、資格確認書、保険証のいずれかをご持参ください。
職場か、加入している社会保険者へ申請してください。被保険者の「非課税証明書」を市役所で取得し、申請書に添える必要があります。
対象とならない場合
- 減額認定証の提示忘れ
- 減額認定証を申請したが間に合わず提示できなかった
- 後から減額認定証を提示した
- 一定の所得があり、減額認定証が交付されなかった
県外の医療機関に入院したとき
県外の医療機関に入院した場合でも、減額認定証の提示や電子資格確認をしていれば、助成を受けられます。自己負担分を立て替え払いし、領収書を保管してください。後日、市でお手続きいただくことにより、翌月以降に支給します。
なぜ制度が変わるの?
在宅での療養を進めていく中、入院されている方と在宅で療養されている方との食事代の公平性を図るためです。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 国保年金課 医療年金係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください