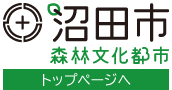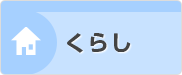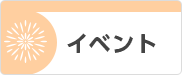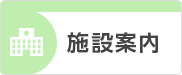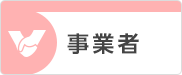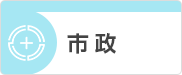よくある質問 固定資産税
【質問1】固定資産税の納税通知書はいつ配達されますか。
回答
5月上旬に、納税義務者の方(共有名義の場合は代表者の方)あてに郵便で配達されます。
郵便配達には数日かかることがありますが、5月中旬を過ぎても届かない場合は、税務課資産税係までお問い合わせください。
【質問2】納税通知書が届かないのですが、なぜですか。
回答
宛所不明で市役所に戻されている場合がありますので、税務課資産税係までお問い合わせください。
【質問3】共有名義の固定資産税の納税通知書は誰に送付されますか。また、持ち分に応じて金額を按分してもらえますか。
回答
代表者あてに送付されます。代表者は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいております。
- 持ち分の多い方
- 市内在住の方
- 登記順位が一位の方
あらかじめ代表者を指定する場合または変更する場合は、税務課資産税係まで申告書の提出をお願いします。
なお、地方税法第10条の2第1項の規定により、持ち分に関係なく共有者全員が連帯して納税する義務(連帯納税義務)がありますので、共有者それぞれの持ち分に応じて課税することはできません。記載されている課税内容をご確認いただき、代表者を含む共有者全員でご協議のうえ、代表者に送付される納付書により納付していただくこととなります。
【質問4】固定資産税の課税明細書(土地・家屋)の見方について知りたいのですが。
回答
土地・家屋の納税通知書には、資産ごとの課税内容を確認することができるよう課税明細書を添付しています。
課税明細書の見方については、お送りする課税明細書の裏面に記載していますが、ご不明な点がある場合には、税務課資産税係までお問い合わせください。
【質問5】納税通知書及び課税明細書を紛失してしまったのですが、再発行はしてもらえますか。
回答
毎年5月に送付する納税通知書及び同封の課税明細書は再発行できませんが、名寄帳(固定資産課税台帳写し)を閲覧(有料、ただし縦覧期間中(毎年4月1日から固定資産税第1期納期限まで)は無料)することで同じ内容を確認できます。
なお、固定資産税を納めるための納付書は再送付いたしますので、ご連絡ください。
【質問6】固定資産税の課税明細書(土地)の畑(介)、田(介)とは何ですか。
回答
宅地介在農地のことで、農地法第4条または第5条の許可または届出を行った畑または田のことをいいます。現況が農地であっても、農地法の規制はすでに外れており、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられることから、固定資産評価基準において宅地並の課税をすることとされています。
【質問7】住所が変わったのですが、固定資産税納税通知書について、何か必要な手続きはありますか。
回答
沼田市内から沼田市内(転居)の場合
市民課市民窓口係に提出していただいた転居届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。
沼田市内から沼田市外(転出)の場合
市民課市民窓口係に提出していただいた転出届の内容が反映されますので、別途手続きは必要ありません。
沼田市外から沼田市外の場合
納税通知書の送付先を変更する手続きが必要ですので、税務課資産税係までご連絡をお願いいたします。
【質問8】固定資産税の納税通知書のあて先を親族や、住所地以外に変更したいのですが。
回答
税務課資産税係までご相談ください。なお、送付先については国内に限ります。
【質問9】所有している土地・家屋が課税されていないようですが、どのような場合に課税されないのですか。
回答
所有する資産が非課税の場合
例:公衆用道路、墓地など
所有する資産が免税点未満の場合
免税点:同一人が市内に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
(土地は30万円、家屋は20万円、償却資産は150万円)
ご自身の資産状況を確認する方法
- 縦覧期間中(毎年4月1日から固定資産税第1期納期限まで)
名寄帳を閲覧することにより、ご確認いただけます。 - それ以外の時期
名寄帳を閲覧することで、ご確認いただけますが、閲覧手数料300円が必要となります。
【質問10】土地や家屋の名義を変更したいのですが。
回答
土地及び登記されている家屋の場合
法務局で所有権移転登記(相続登記等)をしていただきます。
所有権移転登記(相続登記等)が完了すると、法務局への登記内容が市役所へ通知され、手続きが完了した翌年より課税台帳上の所有者が変更されます。
なお、登記の手続が完了した日の確認は、登記簿の受付年月日をご確認ください。
- 沼田市内を管轄する登記所
前橋地方法務局沼田支局
群馬県沼田市西倉内町701番地
電話:0278-22-2518
登記されていない家屋の場合
税務課資産税係へ未登記家屋の名義人変更申告書をご提出いただきます。
名義変更が完了した翌年から、課税台帳上の所有者が変更されます。
【質問11】土地や家屋の所有者(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税についてどのような手続きが必要ですか。
回答
税務課資産税係へ「相続人代表者指定申告書」の提出をお願いいたします。
この申告書は、亡くなられた方の固定資産について、相続人の中で固定資産税に関する書類の受け取り等の代表者を決めていただくもので、所有権を決めるものではありません。所有権を決めるには所有権移転登記(相続登記等)を法務局にて行う必要があります。この所有権移転登記(相続登記等)が賦課期日(1月1日)までに完了すれば、翌年度から新しい所有者に納税通知書を送付いたします。
なお、登記されていない家屋を相続したときは、税務課資産税係へ届出が必要となります。
【質問12】年明けに土地・家屋を取得しましたが、今年の固定資産税は誰に課税されますか。
回答
固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在に登記簿に所有者として登記されている方(未登記の家屋の場合は、家屋補充課税台帳に登録されている方)に対し、その年度分の固定資産税を課税することになっています。したがって、年の途中で土地や家屋を取得した場合であっても、所有している期間に応じて日割りや月割りで課税されるものではなく、あくまで賦課期日現在の所有者に対し、その年度分の固定資産税が課税されます。
【質問13】固定資産税の評価替えとは何ですか。
回答
固定資産税の土地と家屋については、3年ごとに評価を見直すこととされています。
令和3年度に評価替えが行われ、地価や物価の変動に応じて土地や家屋の価格(評価額)を見直しました。次回の評価替えは、令和6年度になります。
【質問14】同じ土地の税額が昨年度に比べて高くなったのですが、どうしてですか。
回答
土地の利用形態が変わったことによる影響が考えられます。例えば、住宅を取り壊して駐車場等にした場合、住宅用地に対する特例措置がなくなった場合に、税額が上昇することがあります。
また、利用形態が変わっていない場合は、地価の上昇や税負担の調整措置による影響が考えられます。
税負担の調整措置について
平成6年度の評価替え以降、宅地の評価は、全国一律に地価公示価格等の7割を目途に評価することになりました。これに伴う税負担の急上昇を抑えるため、なだらかに税負担を上昇させる課税標準額の調整措置が行われています。
具体的には、評価額に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は、税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
【質問15】家屋は年々古くなるのに、なぜ評価額が下がらないのですか。
回答
家屋の評価額は、3年に一度の評価替えの際、「再建築価格(同じ家屋を新築した場合に必要とされる固定資産評価上の建築費)」と「経年減点補正率(年数の経過に応じて生じる減価率で「0.2」が下限となります)」を使って求めます。評価額が前年度の評価額を上回る場合には、原則として前年度の評価額に据え置かれる仕組みとなっています。過去に再建築価格の上昇が続く中、評価額が据え置かれていた家屋は、経年減点補正率を加味しても、以前の評価額を下回らないことがあります。
【質問16】住宅を新築したのですが、固定資産税の減額措置はありますか。
回答
新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合には、一般住宅は新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火構造住宅等は5年度分)、長期優良住宅の認定を受けている場合は新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火構造住宅等は7年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)に係る固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。これらの減額の適用を受ける場合、税務課資産税係へ申告書の提出が必要となります。
減額適用期間の終了後は、本来の税額に戻ります。
要件(1)
専用住宅(専ら人の住居の用に供する家屋)または併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。
なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
要件(2)
床面積要件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
【質問17】家(建物)を新築・増築しました。どのような手続きがありますか。
回答
固定資産税の税額を算出するために、税務課資産税係の職員が訪問し、家屋の間取り・各部屋の仕上げ材、建築設備などの状態などを現地調査させていただきます。
調査の際は、建物内への立ち入りを必要としますので、所有者またはご家族などの代理人の方の立ち会いをお願いしております。
また、図面(建築確認申請書一式や設計図等)の提供をお願いする場合がございます。
なお、訪問する職員は、市職員証・徴税吏員証・固定資産評価補助員証、といった身分証明書を所持しております。
【質問18】家(建物)を取り壊しました。どのような手続きがありますか。
回答
登記されている家屋の場合
法務局で家屋滅失登記をしていただきます。
家屋滅失登記が完了すると、法務局から登記内容が市役所へ通知されますので市役所での手続きは必要ありません。
滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合は、「家屋異動申告書(滅失)」を税務課資産税係まで提出してください。
登記されていない家屋の場合
「家屋異動申告書(滅失)」を税務課資産税係まで提出してください。
(注)取り壊した年の12月末日までに手続きをしてください。固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況で課税されます。そのため、原則として12月末日までに受け付けされますと、翌年度から課税されなくなりますので、ご了承ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 資産税係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください