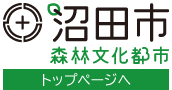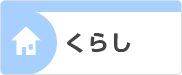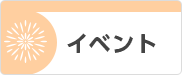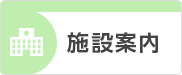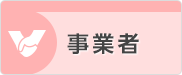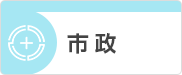ミツバチを飼育する方へ
都道府県への飼育届の提出
- ミツバチを飼育する全ての者は、毎年1月末までに飼育届を住所地の都道府県に提出する必要があります。
届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処されるおそれがあります(養蜂振興法第3条第1項、第4条)。 - セイヨウミツバチ、ニホンミツバチ、どちらも届出が必要です。
- 「自然巣洞」や「重箱式」等の飼育方法でも、反復利用している場合は届出が必要です。
- 飼育届の受理をもって蜂群の配置が許可されるものではありません。
ミツバチの飼育を始める前には周辺のミツバチ飼育者と配置調整が必要であり、調整の結果次第で飼育場所の再検討や蜂群数の減群等を求められる場合もあります。
ミツバチの飼育の際に気を付けること
ミツバチの飼育は、周辺住民や他の飼育者とのトラブルが起こる可能性があるので、注意が必要です。
よくあるトラブル
刺傷事故
ミツバチが人を刺すこともあるため、周辺の人には飼育のことを伝え、理解を得ておきましょう。
特に、春から夏にかけては分蜂防止対策を講じる等、適正な群数の維持に努める必要があります。
フンの被害
ハチのフンにより、周辺住民の洗濯物や車を汚してしまうことがあります。
飼育場所の周辺には十分配慮しましょう。
スズメバチ
秋になると、ミツバチを餌とするスズメバチが巣に飛来することがあります。
スズメバチは攻撃性が強く、周辺の住民が刺されることがあるため、大変危険です。
ふそ病やバロア病(ダニ)などの被害
適切な管理を行っていないと、ふそ病やバロア病(ダニ)などの病気の温床となり、他の養蜂家にも影響を与えることがあります。マニュアル等を参考に適切に管理しましょう。
また、異常が見られた場合は近隣の家畜保健衛生所に連絡してください。
| 概要 | 感染予防 | |
|---|---|---|
| ふそ病 |
ふそ病菌(アメリカふそ病・ヨーロッパふそ病菌)により発症する疾病で、家畜伝染病予防法により法定伝染病に指定されています。ハチの幼虫が病原体を含む餌を摂取したときに発症し、死亡します。 |
ふそ病の発生蜂群は焼却し、本病の蔓延を防止します。盗蜂(ミツバチが他の巣の蜜を盗む行為)も感染原因をなるため発生群の適切な処理が必要です。 |
| バロア病 | ミツバチの外部に寄生するミツバチヘギイタダニによる疾病で、届出伝染病に指定されています。寄生したミツバチを弱らせて養蜂業に経済的被害を与えています。 | 感染予防には、成蜂や蜂児の移動禁止などの管理対策が必要です。 また、寄生したダニを駆除するため、殺ダニ剤による薬剤処理等の対策を行います。 |
トラブルを起こさないために
日頃から周辺の住民の方に対し、ミツバチを飼育することへの理解を得るためにコミュニケーションをとっておくことが重要です。
また、飼育に関する知識や技術を習得することでトラブルを未然に防ぐこともできますので、ご自身で勉強するとともに、地域の実情に詳しい方が行う講習会の受講や、既にミツバチの飼育を行っている方から助言を受けるなど、適切な対応をとるようにしましょう。
問い合わせ先
群馬県農政部米麦畜産課
電話:027-226-3114
農林水産省畜産局畜産振興課
電話:03-3591-3656
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
経済部 農林課 農業振興係
〒378-8501 群馬県沼田市下之町888番地
電話:0278-23-2111(代表) ファクス:0278-24-5179
お問い合わせは専用フォームをご利用ください